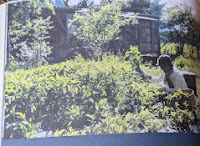プロローグ 旅のはじまり
故郷を出てパリへ、ひたすら墨や鉛筆でドローイングを描いた20代。フォロンのドローイングはありきたりではありません。タイヤが果物になったり星になったり風船になったり。人は背中にゼンマイがついてたり、首から上が鋏だったり、?マークだったり。1980年代にはブロンズで立体化されて、『16番目の考え』(これは頭がプロペラ)という風に名付けられています。65番目まではあるみたい、もっとあるのかな、屋外に置かれたりしているようです。
フォロンはやがて色彩を手にするのですが、それはフランス人アーティストの奥様の影響のようです。(写真は図録より 『無題』)
フォロンの絵のあちこちの登場する、帽子をかぶって大きなコートを着た謎の人物。リトル・ハット・マン。初期のころからずーっと登場し続けます。
海辺に座ってたり、大都会のビルの合間の路上に居たり、掌の上にのってたり、宇宙を飛んでいたり。孤独に、あるいは大勢の中に描かれる。
彼は「私に似た誰か」であると同時に、「誰でもない、何にでもなれる」存在。ニュートラルな存在ですべての人に開かれた存在。やがては描き手のみならず、見る人とも同化する可能性を秘めた存在。
空想旅行の道連れ。
『いつもとちがう』1976年 (チラシ)
1. あっち・こっち・どっち?
フォロンは街が矢印であふれていることを発見します。人間は都市の中でたくさんの矢印に翻弄され、戸惑って行き先を見失っている。案内の矢印は同時にたくさんの方向を示したり、間違った方へ導こうとしているとしたら、どうすればいいでしょう?
「目を澄ませ心を澄ませ矢印を見極め、選び取ることから、空想の旅の第一歩は始まります。」(図録より)
『あらゆる方へ』1970年 (ポストカード)
私この絵好きです。行き先を見失っているというよりは、どちらに行ってもいい、あらゆる可能性に満ちているって感じがします。
2.なにが聴こえる?
フォロンは世界で起きているさまざまな出来事に目を向けます。それは美しいことばかりではない。自然破壊、環境汚染、気候変動、差別、偏見、人権侵害、戦争…。目を覆いたくなるような悲惨な世界を観察し描きます。この時期、彼は政治的風刺的な作品を多数描いています。美しく豊かな色彩のオブラートに包みつつ、静かな怒りを持って。
さて、そんな地球だけど、見上げれば広い空、果てしない宇宙。リトル・ハット・マンは星を見上げ、空を、宇宙を飛び回る。地球は宇宙の一部、「美しい地球を愛したくなる日もあるのだ。」ともフォロンは語っています。」(図録より)
『深い深い問題』1987年(図録)
この絵は後に環境団体グリーンピースのポスターになりました。海の中を、魚ではなく魚雷の群れが泳いでいます。
3.なにを話そう?
フォロンは「タイム」「ザ・ニューヨーカー」などの雑誌、オリベッティなどの企業広告、公共団体(例えば環境団体グリーンピース、輸血・移植・免疫センター、人種差別反対など)・イベントなどのポスターを多く手掛けています。
多くの人の目を捉え、心に残るようにとシンプルさを心がけ、絵と見る人が対話することを望んでいました。
1988年、フォロンはアムネスティ・インターナショナルの「世界人権宣言」の挿絵を制作します。この表紙の絵、見たことある方、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。
序文から30条までのうち19項目を水彩画で、原画と、そのためのスケッチが共に展示されています。
意外だったのは、明るい未来が描かれているのかと思いきや、そうではないこと。描かれた絵は、権利や自由がないがしろにされた現実世界を象徴しているのだとか。なるほど。
上の写真『世界人権宣言 表紙原画』1988年
下は、左上『第14条 逃げるのも権利』
右上『第15条 どこの国がいい?』
左下『第18条 考えるのは自由』
右下『第19条 言いたい、知りたい、伝えたい』
挿絵原画 1988年(すべて図録より)
エピローグ.つぎはどこへ行こう?
フォロンは1968年からパリ郊外の農村で暮らしました。どこまでも広がる平原の向こうの地平線を眺めながら。1985年には、南仏のモナコにもアトリエを作りました。そこでは海の向こうの水平線を眺めて。
空と大地、空と海が接する景色はフォロンの作品の根幹をなしています。
ある時、フォロンは明け方に現れた太陽を巨大な人物の目と感じる体験をします。地球を見渡し、穏やかに見つめる未知なる創造者の視線。それを見上げるリトル・ハット・マン。「世界は毎朝生まれ変わり、旅はどこまでも続いていく。」(図録より)
写真は 『対話』1975年 (ポストカード)
フォロンは鳥に憧れ、空を自由に飛んで風や空と話してみたいと思っていたと言います。自分以外の何になりたいかと問われれば、鳥と答えていたそう。鳥は自由のシンボル。フォロンはいつしか、想像力という翼を持ち、時空を飛び越える真の自由を得たのでしょう。
リトル・ハット・マンと同化したフォロン、空を飛び宇宙へと旅立っていきました。
「2005年10月、フォロンは71歳で世を去りました。謎多くして愛すべきこの世界、そして人間という存在を探求し続けた人生の旅路を終え、自由な鳥となって。」(図録より)
『月世界旅行』1981年 (図録より、この作品は今回の展覧会のチラシにも使われています。)
鑑賞の後のビール。ベルギー人のフォロンに敬意を表して(?)ベルギービールを。
この日は夫ではなく、東京在住の女友達と行ったので、丸の内の「ベルジアン ブラッスリーコート アントワープセントラル 」でランチ食べながらおしゃべり。ベルギービールの定番シメイやデュバルを飲んできました。
ベルギービール、やっぱりおいしい!その昔、仙台に通ってた頃、仙台メディアテークのカフェでよくベルギービール飲んだこと、懐かしく思い出しました。
★番外編 美術館じゃなくて映画ですが。
とある夏の暑い日、蘇我の映画館・Tジョイ蘇我で『めくらやなぎと眠る女』を見ました。原作村上春樹、監督ピエール・フォルデス、アニメ映画です。これがなかなかのものでした。村上春樹のミステリアスな雰囲気を残しつつ、現実と幻想の入り混じった不思議な世界がうまく視覚化されています。村上春樹お好きな方、一見の価値ありです。
*「めくらやなぎと眠る女」はユーロスペース他で上映中。千葉では9月14日から柏のキネマ旬報シアターで上映されます。
そして映画の後には、蘇我にあるクラフトビール「潮風BrewStand Soga」へ。こちらは12tapの個性的なラインナップ。千葉にもおいしいクラフトビールあるんだ、と再認識。また探して行ってみようと思います。
夏はビールがおいしい! 夏じゃなくてもおいしいけどね。 (2024年8月30日 佳)
参考 「空想旅行案内人 ジャン=ミッシェル・フォロン」図録